これは、わが家で日常茶飯事だった、三姉妹のうち上二人である、小学校高学年の長女と小学校中学年の次女メインの姉妹喧嘩エピソードです。
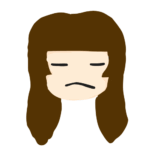
ママー、また次女が勝手に私の服着てる!!

ママー、姉ちゃんがまた次女のことつねってきた!!

ママー、また長女と次女が喧嘩してる!!

えーまた喧嘩…いい加減にしてくれ…
仲良く平和に暮らしたいところですが、なぜかわが家の子どもたちは、些細なことから喧嘩が頻発します。
ネタはその時によって違いますが、私や旦那までイライラしてしまい、夫婦喧嘩にまで発展することも。姉妹喧嘩が起こると家の雰囲気が悪くなり困っていました。
姉妹喧嘩は性格や発達の違い、外でのストレスなど子どもなりの理由がある自然な現象で、仲が悪いからではなかったのです。
姉妹喧嘩について研究していく中で、子ども目線で原因を知ることで、怒らず理解する関わり方ができるようになり、喧嘩に対する見方を大きく変えることができたのです。
「今日もまた喧嘩…」といやになっているママやパパにとって、少しでも参考になればうれしいです。
小学生の姉妹喧嘩が起こる5つの理由【親が知っておきたい背景】

姉妹喧嘩がおこる理由は大きく分けて以下の5つが主です。
- 性格や気質の違い
- 年齢差による発達のギャップ
- おもちゃ・テレビなど「モノの取り合い」
- 親に注目・かまってほしい
- 学校など日常でのストレスを家庭で発散している
姉妹喧嘩は「仲が悪いから」ではなく、性格や発達の違い、外でのストレスなどの理由からくる、自然な現象だったのです。
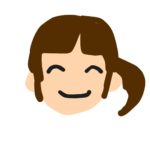
子どもの気持ちに寄り添った対応を勉強して、家族みんなが気持ちよく過ごせるようにしたいところです
理由①性格や気質の違い
姉妹でも、好き嫌いや頑固さ、話し方などの性格の違いがありますよね。お互いが、自分の世界を主として考えているために、違いが理解できず、衝突がおこるのです。
同じ親から生まれた姉妹とはいえ、性格や気質は個々でまったく異なります。
慎重派・大胆派、マイペース・せっかちなど、性格の違いが衝突の原因になることは多いです。
どちらかが悪いわけではなく、ただ単に「合わないだけ」が原因もありえます。
親がどちらが悪いと結論付けるのではなく、相性や性格の違いと受け止めることが、イライラを軽減させる一歩です。
理由②年齢差による発達のギャップ
年齢が2歳違うだけでも、言葉の使い方やルールの理解度に差があります。
自分は気を付けているのにどうしてわからないのかわからない、こんなのすぐできるのにまだその状態?といったズレからイラ立ちが募り、喧嘩に発展するのです。
成長段階を考えて、上の子・下の子それぞれに合った接し方や投げかけを行うと、誤解や不公平感を減らせます。
理由③おもちゃ・テレビなど「モノの取り合い」

子どもにとって「自分のモノ」への執着は自然なことですが、まだ相手の気持ちを考えて仲良く共有するのは難しいので、喧嘩になってしまいます。
「モノの取り合いはトラブルではなく社会性の練習」と捉え、子どもがモノの取り合いで喧嘩するのは当たり前だと考えましょう。
また喧嘩している…と考えるのではなく、成長段階で自然に発生していると知り、関わるときの心に余裕を持ちましょう。
理由④親に注目・かまってほしい
喧嘩の裏には「もっと自分を見てほしい」という愛情確認の行動が隠れていることもあります。
特にわが家の次女が喧嘩を仕掛ける原因はこのパターンが多いです。
子どもの心のサインを見逃さずに、叱る前に寄り添うことが、このパターンでの喧嘩を穏やかに収束させる大前提です。
理由⑤学校など日常でのストレスを家庭で発散している
学校での緊張や不満が、家で安全に発散される結果、姉妹間の衝突につながることがあります。
喧嘩の背景に「外でのがんばり」があると知っておけば、姉妹両方の気持ちに共感しやすくなりますよね。
このパターンでは、「今日は学校どんなことをしたの?」や「一日学校で頑張って疲れたよね」といったねぎらいや共感が収束の第一歩です。
私自身仕事で疲れて帰宅し、ちょっとしたことでイライラしてしまっているとき「ママ仕事で疲れているんだよね」と三女に声をかけられて心が軽くなることがあります。
姉妹喧嘩への親のベストな対処法5選

姉妹喧嘩が発生したとき、すぐに止めようとせず、状況を見極めて関わり方を変えることが、姉妹の関係改善につながります。
状況の見極め方と、その時の対処方法をご紹介します。
- 初期段階:すぐに仲裁せずまず見守る
- 暴力発生:手や暴言が出たときには冷静にルールを伝える
- 喧嘩収束:喧嘩後に一人ひとりと話す時間を作る
- 喧嘩防止:共同作業や一緒に楽しむ時間を意識的に作る
- 親のケア:親が辛い時は逃げてもいい
状況判断ができるようになり、声のかけ方や距離の取り方を意識することで、感情的に怒らなくて済むようになりますよ。
初期段階:すぐに仲裁せずまず見守る
すぐ親が仲裁に入って止めるのではなく、自分たちで折り合いをつける経験は姉妹の関係を強くします。
子ども同士で問題解決をする力を育てるためには、親の距離感が非常に重要です。親の介入を減らすと、子どもたちが自分で考えて話し合う力が自然に育ちます。
ヒヤヒヤするからといって過保護に干渉することは、意外と子どものためにならないと自分に言い聞かせます。
ちょっとした言い合いなど、喧嘩の始まりは、暴力などの危険が伴わなければ、両者でどのように折り合いをつけていくのか見守るのがベストです。

ヒヤヒヤしたり、いつ止めに入ろうかと思いますが、最初はぐっと我慢して見守る、ですね
暴力発生:手や暴言が出たときは冷静にルールを伝える
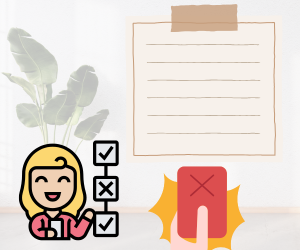
親の距離感が必要とはいえ、危険を伴う場合は放置厳禁です。
心身が傷つく可能性のあるトラブル状態に陥っている場合は、その場でストップさせましょう。
ストップするときに怒鳴るのではなく、落ち着いて「手を出すのはいけない」「言っていいことと悪いことがある」と伝えましょう。
暴力や暴言は放置せずに「やってはいけないこと」として親が冷静に示すことが重要です。
感情的に怒るのではなく、家庭に誰でもわかる、外でも使える、「人としての基本ルール」を育てていきましょう。
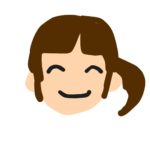
止めに入るのは、暴力や暴言が発生した時、と覚えておきます
喧嘩収束:喧嘩後に一人ひとりと話す時間を作る
喧嘩の時こそ、喧嘩して「どう感じたのか」「どうしたかったのか」を振り返り、自分の言葉で説明し、一緒に整理すると信頼関係を深められます。
意見を聞き出して言葉で説明させることは、子ども自身が自分の気持ちを整理できることに繋がるのです。
感情を言葉にして表す練習ができ、子どもの自己理解や相手を理解する力を自然と育てることができます。
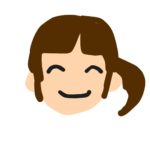
喧嘩した姉・妹両方と個別に「なんで喧嘩になったのか」「どうしたかったのか」を聞いて、心の整理をさせるサポートをしていきます
喧嘩防止:共同作業や一緒に楽しむ時間を意識的に作る
一緒に楽しく過ごす時間を増やすと、自然と仲良しの時間も増えます。
わが家では、トランプや折り紙をして楽しむことが多いです。料理のお手伝いをしてもらったり、一緒にゲームをして過ごすのもいいでしょう。
仲良く過ごす場を増やすと、仲良くする練習にもなりますし、喧嘩の予防や姉妹の絆を深めることにもつながります。
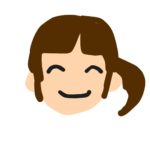
楽しいイベントがある日に姉妹が結束して平和に過ごせることが多いのは、共通の感情が理由だったのだと感じました
私自身も平和に過ごすために、寝る前の隙間時間に家族でトランプをしたり、ゲームを一緒にする時間を意識的に作るようにしています。一緒に楽しむ時間って大事ですね。
親のケア:親がつらい時は逃げてもいい

親が限界の時は、喧嘩に対応せずその場を離れたり、誰かに頼ることも立派な選択肢です。
私は、長女と次女の喧嘩にいら立ってしまうとき、あえて三女に相談することもあります。
親がちゃんとしないと…と考えすぎると、自分自身ももちろんですが、子どもの精神衛生上も、えよくありません。
穏やかに接する、温かい空気を作るママを演出するためにも、自分が限界のときは逃げるが勝ちと考えています。
親も人間ですので、どうしても無理なときやこのままだと子どもの前で平静を保てないときには、気持ちを切り替えてから対応しましょう。
わが家の姉妹喧嘩エピソード3選

自由で個性の強い三姉妹がいるわが家で、これまでに発生した喧嘩は数えきれないほどです。
長女と次女は2歳差、次女と三女は4歳差ですが、原因は年齢差による理解の違いだったり、性格による考え方の違い、親の取り合いなど様々です。
ここでは、わが家姉妹喧嘩エピソードを3つご紹介します。
- 次女が長女にマウント
- 長女が次女を意のままに
- 親から注目されている姉妹への嫉妬
それぞれ原因が異なりますが、解決方法は個々と話をして、状況をお互いに理解し、同じパターンの時にどう行動するかを決めることです。
次女が長女にマウント
次女は活発で男勝りな性格です。リーダーになりたい欲望があり、おっとりした長女を見下しているときがあります。
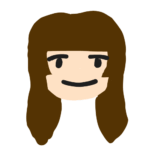
三女ちゃん、一緒に遊ぼう!まずはこれをこうして…
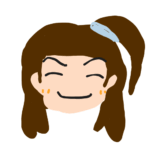
姉ちゃんそんなやり方じゃ遅いって!もっとこうしたほうがいいって!!

ねえ、長女と次女どっちのいうとおりにしたらいいの?
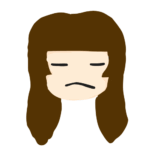
次女!!私が誘ってやり始めたんだから勝手に横から指図しないで!!

いやいや姉ちゃんのやり方おかしいやろ!絶対次女の言うとおりにした方がやりやすいって!!
次女はおっとりした長女の自分と違う考え方が受け入れられず、自分の考えが一番正しいと考えている部分があるので、長女のやり方をよく否定します。
日常茶飯事の喧嘩も、原因が考え方の違いだと理解できると、解決策として個々に考え方の違いを認めるサポートの投げかけをすることができます。
長女が考えてやり始めたことを理解せずに、自分の考えが一番だと考えないよう、次女にお話しをしました。次女自身、自分と違うやり方も間違いではないことを知る一歩になりました。
長女が次女を意のままに
長女は、自分が一番のお姉ちゃんだと自負しており、年下は年上の話を聞くことが絶対だと考えてしまう傾向があります。
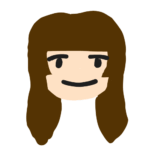
ねえ次女、ここにあるもの片付けておいて

えー!姉ちゃんも使ったやん!どうして次女だけで片付けなん?
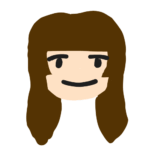
え?一緒に遊んであげたんだから、それくらいやってもいいでしょ

ママ-!!姉ちゃんが一緒に遊んだのに片付けだけ次女にやれっていうのおかしくない?
ここで私は、長女と一対一で話し、長女に遊ぶのは誰がしたかったことかを確認しました。長女自身が遊びたくてはじめたとの答えが返ってきました。
長女自身が遊びたくて始めたなら、次女に対して「遊んであげた」表現は事実と違うこと、遊んだら一緒に片付けをしてほしいことを伝えて、この場は一緒に片付けをすることで収束しました。
今回の長女が次女を意のままにする行動は、長女という立ち位置で日頃抱えているストレスを次女にぶつけていることが原因でした。
「お姉ちゃんだから」と長女に手伝いなどをお願いしていることが負担になっていることを知り、家族の仕事分担の量を均等にする必要があると話し合ういいきっかけになりました。
親から注目されている姉・妹への嫉妬
いいことをしたら褒めますが、わが家は狭くタイミングを狙う時間の余裕もなく、その場で他の姉妹が褒められているのを目にして気分を悪くすることがありました。
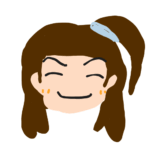
ママこれ見て!!(100点のテストを持ってくる)
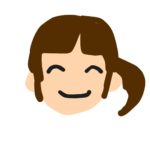
おお!全部正解している!やったね!!
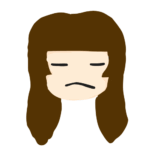
いちいち褒められようとして目の前で…!!
数分後…次女がお風呂に行こうとすると、お風呂前の通路に立ちふさがって通せんぼをする長女がいました。

姉ちゃん!!そこ通してや!!
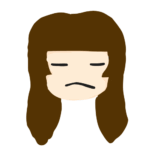
なんで?あんたママに褒められようとしていちいちウザい!!
私自身は次女も長女も同じ内容のことで褒めているつもりですが、今回は次女がたまたまテストを持って帰っており長女にはコミュニケーションをとっていませんでした。
長女は次女が私に褒められているのを見たあとに、嫌がらせをはじめてしまいました。
今回の原因は、長女が次女のみ親から注目されており、自分はかまってもらっていないことによる嫉妬でした。
ここでは長女と一対一で話をして、どの娘も私にとって大事な娘であることを伝え、長女が100点のテストを私に見せたときの私の対応を振り返ってもらいました。
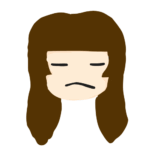
今日ママ私には、なにも褒めてくれなかったじゃん
子どもはまだ考えが自分本位なので、日々その時の各々が一人だけが大事にされていると感じてしまわないような関わりのさじ加減や、他者の気持ちを考える投げかけを意識するようになりました。
姉妹喧嘩が減ったわが家のちょっとした工夫

特別なことをしなくても、ちょっと意識して工夫するだけで、喧嘩を減らしたり、喧嘩をおちつかせる環境づくりに繋がります。
実際にわが家が取り入れて、効果のあった3つのポイントをご紹介します。
- 1日1回一緒に楽しむ時間を意識する
- 一人一人と過ごす時間を1日に少しでも作る
- 「どちらが悪い」ではなく「どうしたい」「どう思う」を聞き出す
ぜひ姉妹喧嘩で参っているあなたに、だまされたと思って試してみてほしいと思います。
特に喧嘩が発生した時に個々の意見を聞くこと、3人それぞれと過ごす時間を意識すること、3人とともに楽しむことは日々意識するようにしています。
少しの意識ですが、いやになって放置するより、長い目でみても効果的です。
工夫①1日1回一緒に楽しむ瞬間を意識する
忙しい日でも「笑った」「楽しんだ」記憶は、姉妹の関係を優しくします。
大したことでなくても、同じ出来事について感情を共有した経験を1つ1つ積み重ねることが大事です。
ママがシャツを裏表逆に着ていたといった大したことではないけれど笑っちゃうような出来事を一緒に味わうだけで、同じ感情を共有でき、絆を強めることにつながるのです。
毎日続けやすい無理のないかかわり方で、姉妹の空気がぐっと良くなるだけでなく、自分自身も楽しく過ごせます。
工夫②一人ひとりと過ごす時間を1日に少しでも作る
「私を見てくれている」という実感は、子どもに安心感を与え、喧嘩を減らすことに繋がります。
1日5分でもOKです。
私自身はそんなつもりがなくても、子どもは「私は親からあまり気に留められていない」と感じられていることは多く、かまってほしいために喧嘩のもとになってしまいます。
問題に対応している私を見て、「自分のことを見てくれている」と感じてしまい、コミュニケーション不足の時は、必ずと言っていいほど喧嘩がおこります。
あまり多くの時間を割くことは難しいですが、3姉妹それぞれに「今日は何したの?」「明日はどういう予定?」など何か1つは話しかけることを心がけています。
工夫③「どちらが悪い」でなく「どうしたい」「どう思う」を聞き出す

私は今まで、喧嘩や衝突が怒ると問題としてつまみ出し、原因を追究して改善しようとしていました。
誰かを悪者にするのではなく、気持ちの整理に集中する方法は、姉妹関係悪化時の早期回復に繋がります。
裁き正すのではなく、気持ちを言葉にして共有することで、姉妹の間に共感が生まれ、自分の感情を整理する力も高まります。
あえて善悪のジャッジでない対話を重ねることは、親子関係も姉妹関係も深まる体験につながるのです。
よくある姉妹喧嘩のQ&A

「どこまで介入するべき?」「片方ばっかり怒っていいの?」などの親の迷いは多いものです。
しかし、「子どもの気持ちが動くポイント」を知っておくと、対処は難しくありません。
- ケース①勝手に姉の服を妹が着て姉が怒っている
- ケース②姉妹喧嘩は姉を怒るべき?
- ケース③おもちゃの取り合い
- ケース④親の見えないところで喧嘩…
よくあるケースで我が家が取り入れて上手くいった対処方法をご紹介します。
ケース①勝手に姉の服を妹が着て姉が怒っている
- Q勝手に姉の服を妹が着て姉が怒っています。
- A
妹に、服の所有者が誰か確認しましょう。もし自分のモノではないとわかっているのに使っているときは、「自分が勝手に使われたらどう思う?」「お姉ちゃんは着てほしくないんだって」と伝えましょう。もし自分のモノだと思っていたり、姉のものと知らなかったときは、姉のものだから自分のを使うように伝えましょう。
また、性格が違い妹は姉に自分の服を着られても怒らないけれど、姉は自分の服は自分だけで使いたいという価値観が違う場合もあります。その場合も、お互いの考え方が違うために相手にされて嫌だと感じる内容が違うことを考える時間を作り、いやなことを起こさないようなルール(今回なら自分の服以外は勝手に着ないというルール)として決めてしまうと再発防止につながります。
ケース②姉妹喧嘩は姉を怒るべき?
- Q姉妹2人で遊んでいるときに喧嘩になったら、姉を怒るべき?
- A
姉妹喧嘩が怒ったからと言って年上を怒ることは、年上の子どもとの今後の親子関係悪化を招く可能性があります。どちらが悪は決めず、姉妹それぞれがどうしたかったのかを聞き、姉妹それぞれの感情を言語化してまとめ、次に同じようなことになったらどう行動するかを話し合いましょう。
話し合って決まった内容は、家族みんなが見える場所に貼りだしたり、話し合いをした家族のメンバー以外にも共有しておくと、後々問題になることが少ないです。
ケース③おもちゃの取り合い

- Qおもちゃの取り合いをして、つかみ合いをはじめました。どのタイミングで介入すべきですか?
- A
おもちゃの取り合い自体は社会性を身に着ける重要な機会ですが、相手をたたく、相手に暴言を言うといった言葉もしくは体の暴力が発生した時に介入し、暴力はいけないことを伝えましょう。
おもちゃの取り合いのみなら、見守ってどう解決しようとするのかを見るのがいいです。つかみ合ってけがをする可能性が出てきたり、言葉での暴力が発生した場合には、冷静に話せる大人が仲裁に入り「やっていいことといけないこと(相手の体を傷つける暴力)」「言っていいことといけないこと(相手の心を傷つける言葉)」は感情を挟まずに伝えることがポイントです。
ケース④親の見えないところで喧嘩…
- Q親の見えないところで姉が妹を攻撃しています。
- A
攻撃を仕掛けている側は、何かしらで不満を募らせており、相手にぶつけて発散している可能性があります。まず、攻撃側と一対一で話をして、日頃感じていることや、不満に思っていることを聞き出しましょう。ただ何となくで起こった場合は、やっていいことといけないことがあること、次起こったら何かしらの対策をすることを話します。攻撃側が不満に思っていることを聞き出せたら、その感情を親と姉妹の三者で共有し、問題を再発しないためにできることを姉妹それぞれから聞き出して合意しましょう。
もし、原因が姉妹片方の親からの愛情量に対する嫉妬である場合は、親の関わり方のバランスもポイントです。姉にだけ、妹にだけ何か違う対応をしているのであれば、公平な対応をするのもよいでしょう。また、姉妹の片方が見えていない、知らない、わかっていないだけの場合もありますので、よく話し合ってお互いが納得して安心できる話し合いが大事です。子どもにどう関わってほしいかを聞き、親自身の関わりの量も意識することで姉妹が納得できて緩和するケースもあります。
まとめ

- 姉妹喧嘩は性格や発達の違い、外でのストレスなど子どもなりの理由がある自然な現象で、仲が悪いからではない
- 小学生姉妹喧嘩の主原因5つは①性格や気質の違い②年齢差ゆえの発達ギャップ③モノの取り合い④親の関り不足⑤日常のストレス発散
- 姉妹喧嘩への対処方法は発生するタイミングと状況によって異なり、すぐに仲裁しようとせず暴力が発生した時は冷静に止めに入るのがよい
- 姉妹喧嘩から成長をするために、個々と感情がどう動いたかの話をして子ども自身の言葉で説明させるとよい
- 姉妹喧嘩で親が疲れてしまっているときは、無理に喧嘩を仲裁しようとするのではなく、あえてその場を離れたり他の人に相談・解決を頼ることも〇
- 姉妹喧嘩自体を少なくするための工夫3つは①1日1回は一緒に楽しむ瞬間を作る②一人ひとりと過ごす時間を1日に少しでも作る③喧嘩が怒っても悪を決めずどう考えたかを話し合う
姉妹喧嘩は「成長の通過点」なので親が全ての問題を背負う必要はないです。ときには離れて見守るほうが成長を助けることもあります。
姉妹喧嘩が起こる理由や背景を知って、親が関わり方を工夫すると、少しずつ姉妹喧嘩の頻度を減らし、穏便な解決ができるようになってきています。
喧嘩はお互いが話し合い、考えを共有し、相手の立場を考えることを練習していくことが大事だなと感じる日々です。
わが家では怒りが発生した時に、怒りのままに相手を攻撃することが多いので、そうならないよう感情をぐっと我慢するアンガーマネジメントも今後取り入れていこうと考えています。
私のように小学生の姉妹喧嘩に困っているあなたも、対処法を取り入れて姉妹喧嘩で悩む頻度が減り、幸せな瞬間が増えたら嬉しいです。

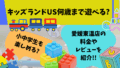
コメント